
|

|
|

牛飼いの家の朝は早く、暗いうちから牛の乳を洗い、乳絞りの準備をする。その日も一仕事終えた親父さんは、朝酌を済ませて玄関脇の和室で眠った。煙いので、タバコの消し忘れかと思って目を覚ましたら、すでに一面の煙。居間側の引き戸を開けたら、ものすごい熱の空気が吹き込んできて「火事だ」とようやく気がついた。居間に逃げるわけにもいかず、床の高さについていた下地窓を外の格子もろとも蹴破って、家の外へ脱出したという。一階七十坪、二階三十坪、合計百坪の大きな木造の牛飼いの家は、家の真ん中にあった吹き抜けを煙突のようにして、大きな炎を立ち上げると瞬く間に焼け落ちたという。牛舎にいた奥さんも燃え上がってから気がついたという。
二十年近く前に「自然に逆らわないような家を」といわれて造ったものである。「折角造ってもらった家を燃やしちまって申し訳ない。家に使った材料が本物ばかりだったので、煙でやられることも無くて、ほんとに助かった。無駄だと思った下地窓も、逃げるのに役に立ったしさ。命があるのも先生のお蔭さ」といわれて、恐縮した。 あまりの炎の勢いに、交差点の向こうの農家に火が移らないかと、心配したという。プレハブの仮設の小屋で寝起きしているが、あっという間のことで、なんにも持ち出すことができず、大きな仏壇から家財道具のほとんどを焼いてしまい、眼鏡や入れ歯の果てまで燃えてしまった。寝巻きのほかに着るものが無い。千歳の冬は厳しいから、年内に引っ越せるようにしてくれという。今度は、もっと小さい家にしようと勧めるが、なんだかんだでほとんど同じ大きさになってしまった。しかし、古い基礎をそのまま使ったりして、お盆明けには上棟式ができたので、正月は新しい家で迎えられそうである。これができるのも、二十年にわたって、きちんと十分な保険をかけ続けていてくれたお陰である。 保険のありがたさと、まさかのことの重大さを実感した。
住宅雑誌リプラン・66号より転載
|
|
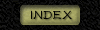
|

|